こんにちは、かしゅーです。
私は双極性障害を抱えながら、研究開発職として働いています。仕事の中で精密な作業をする業務のときは、ほんの少しのズレも許されず、常に神経を張り詰めなければなりません。そんな中、私の生活には欠かせない薬、炭酸リチウムがあります。リチウムは気分を安定させるために非常に有効な薬ですが、一方で手の震えや判断力の低下など、副作用が出ることもあります。
私自身、手の震えをはじめ、言葉が出にくくなる、判断が鈍るといった症状に悩まされてきました。特に職場での精密作業中は、「失敗できない」という緊張感がさらに症状を強めます。自分の判断力が薬や病気の影響で低下しているのではないか、と不安になる日も少なくありません。
リチウムの副作用と向き合う
リチウムは一生続けなければならない薬と思われがちですが、正確には「必要な範囲で適切に服用すること」が重要です。副作用が強く出る場合は、薬の量や服用方法の工夫で症状を軽減できる可能性があります。私の場合、手の震えはリチウムの副作用であることを理解し始めました。その上で、生活の工夫と主治医との相談を通して、症状を最小限に抑える方法を模索しています。
たとえば、リチウムの血中濃度を安定させるために水分量の管理が有効です。水分が不足すると血中濃度が上がり、手の震えやふらつきが強くなることがあります。逆に、十分な水分をとることで、血中濃度の急上昇を防ぎ、副作用を和らげることができます。ただし、水分量を自己判断で極端に変えるのは危険です。必ず主治医に相談しながら調整することが大切です。
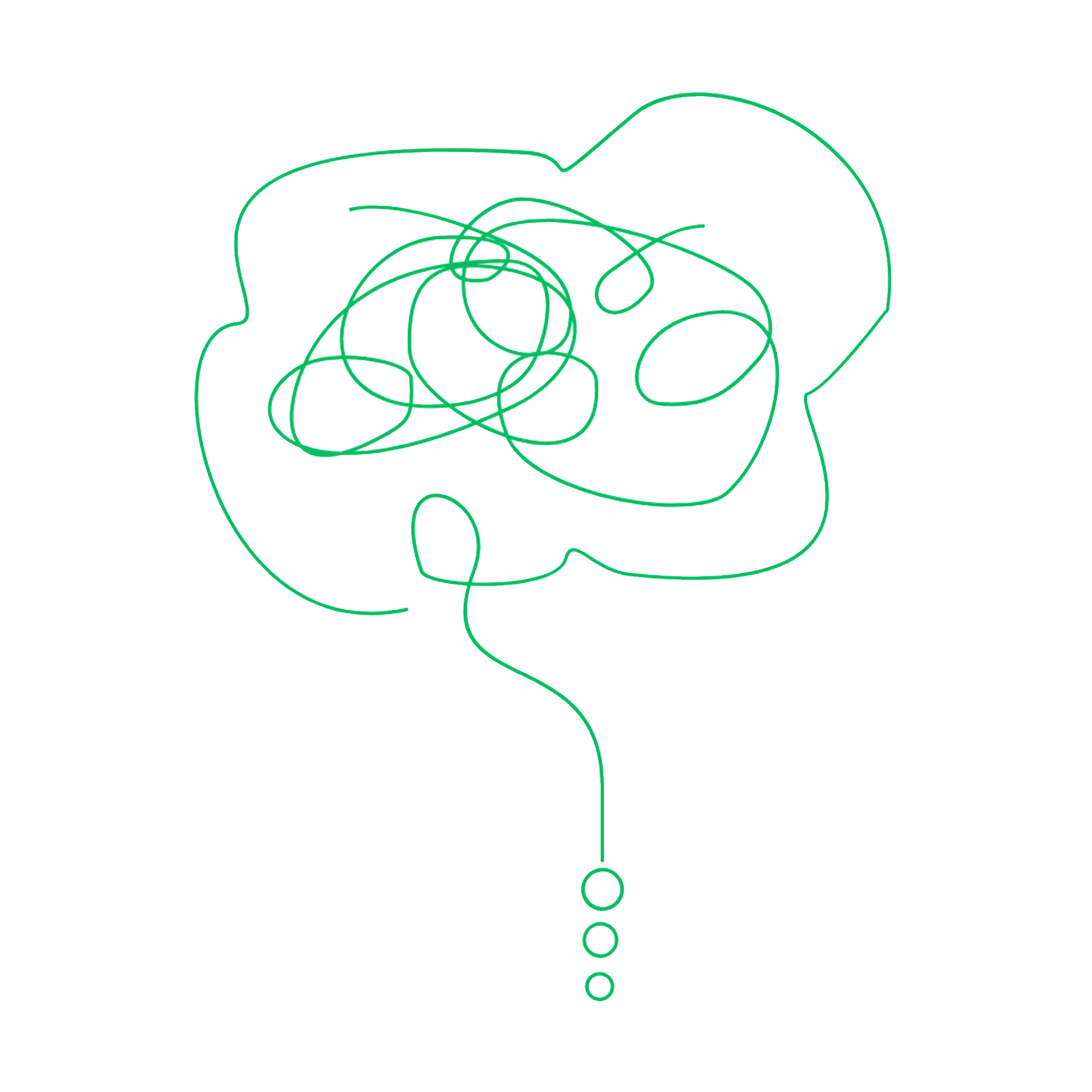
手の震えという症状は緊張したり、寒かったりすれば誰しも起こるものではないですか?



それが病気的にあるイメージですね。私の場合ご飯を食べることや、パソコンで仕事をすることも困難になるときがあります。
私は主治医との相談の際、短い診察時間でも要点を整理して伝えるようにしています。事前にメモを作り、手の震えや集中力の低下、作業中の緊張感などを具体的に伝えます。「薬は続けたいけど、副作用を少し和らげる方法があれば相談したい」と率直に話すことで、医師も的確なアドバイスや調整をしてくれます。診察で伝えたい内容を整理しておくと、たった5分の診察でも十分に相談が可能です。
精密作業の中での心構え
職場では、「失敗が許されない」という空気が漂っています。その中で、同僚と自分との能力差や、病気の影響による不安感に押しつぶされそうになることもあります。私も、「自分は能力が低いのではないか」と自己否定しがちです。しかし、重要なのは「失敗を恐れすぎず、自分にできる範囲で丁寧に取り組むこと」です。
緊張感が強いと、手の震えや思考の停滞が起こるのは自然な反応です。これは弱さではなく、心身が危険を察知しているサインです。まずは「今日は出勤して作業に取り組めた自分」を認めることが、精神的な負担を和らげる第一歩になります。また、作業中は一度に全力を出すのではなく、集中できる範囲や時間に分けて取り組むことで、体と心の負担を減らすことができます。
情報収集と理解で不安を減らす
双極性障害やリチウムの副作用について正しい知識を持つことも重要です。情報を整理することで、「なぜ手が震えるのか」「判断力が鈍るのか」を理解でき、不安が軽減されます。
最近読んで特に役立ったのが、双極性障害の理解を深める書籍です。例えば『双極性障害』(ちくま新書)では、病気の仕組みや薬の作用、副作用の対処法などが具体的に説明されており、実生活に即したアドバイスが得られます。このような書籍を参考にすることで、自分の症状を客観的に捉えやすくなり、医師との相談にもスムーズにつなげられます。
さらに、最近ではオンライン診療や薬管理アプリを活用することで、副作用の記録や服薬管理が容易になっています。私自身もアプリで手の震えの度合いや作業中の集中度を記録することで、医師に具体的なデータを示し、薬の調整の参考にしています。これにより、ただ不安に押しつぶされるのではなく、自分の状態を数字として客観的に見える化できるのが大きな安心材料になっています。
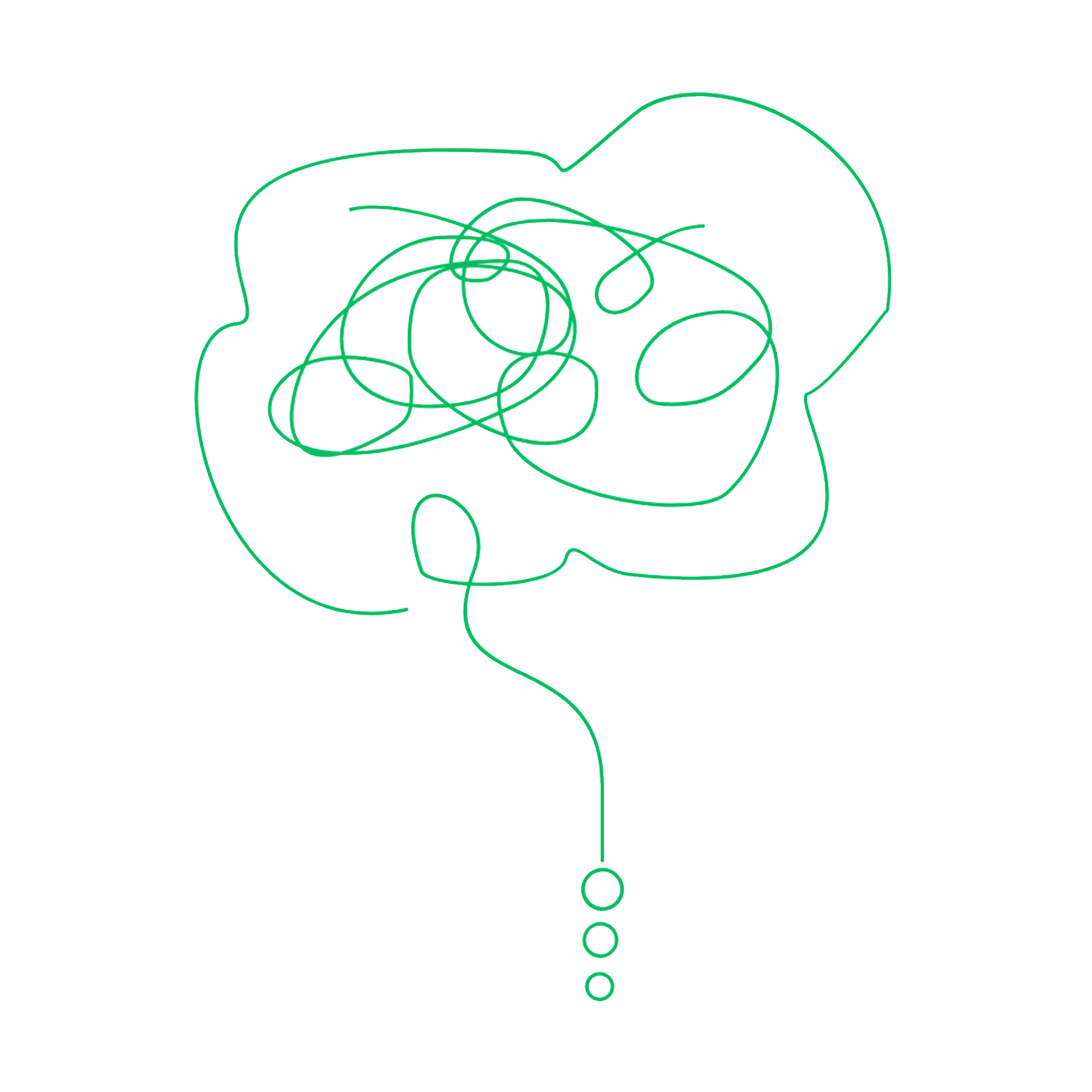
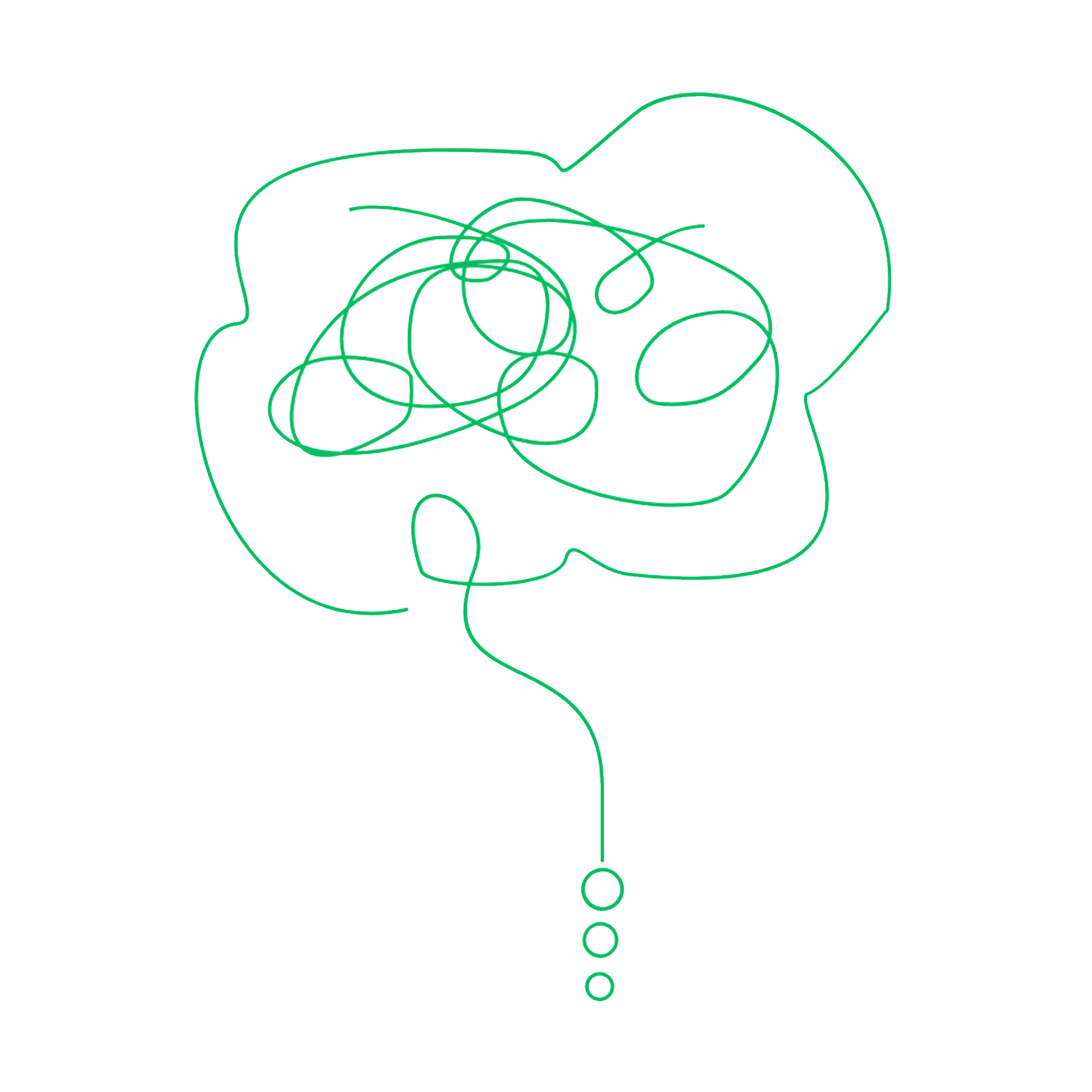
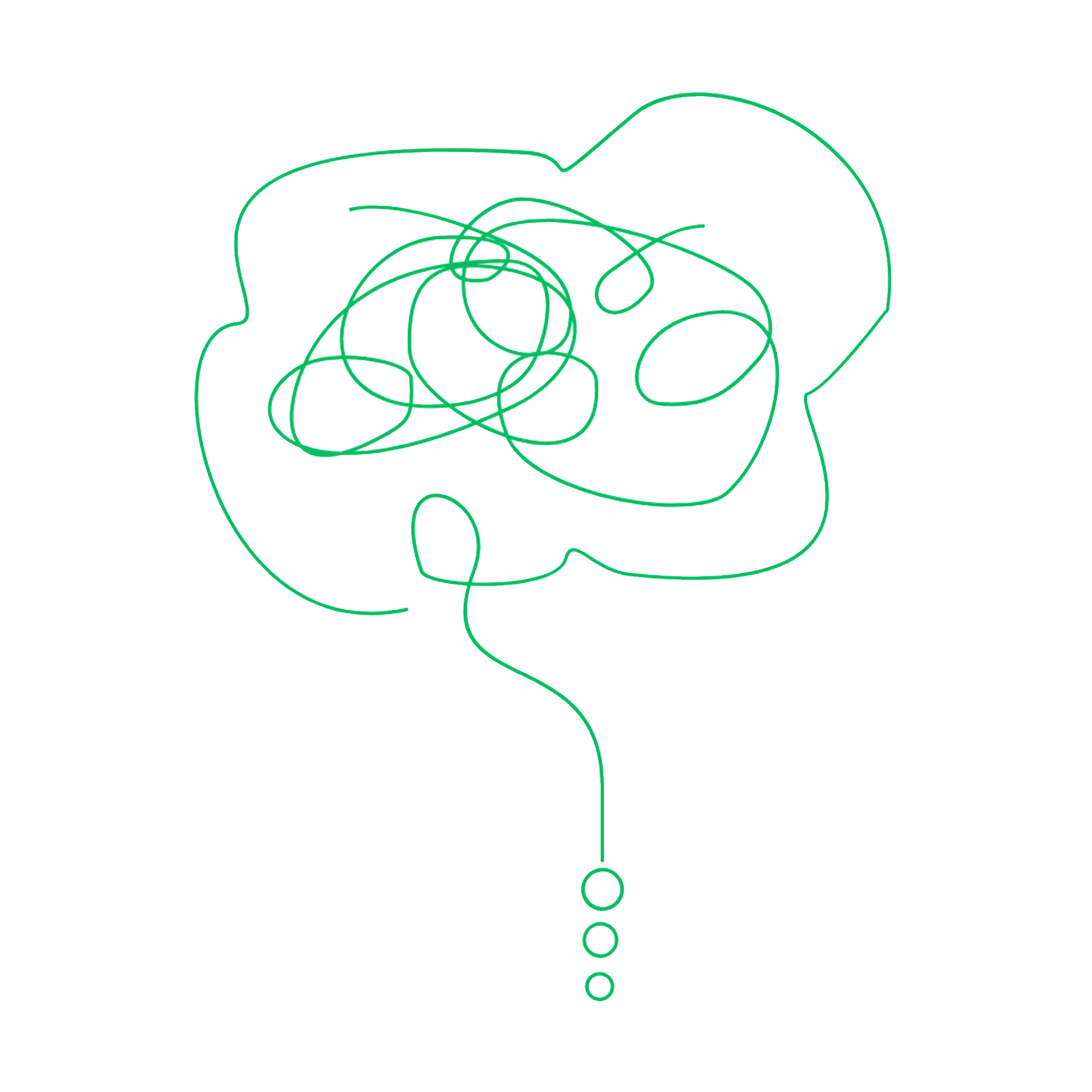
気分の上がり下がりを記録するのに良いアプリはありますか?



私は「Moodistory」というアプリを使っています。
薬を続けながら働くコツ
- 副作用を理解する:手の震えや集中力低下は薬の影響。自己否定しないこと
- 医師と相談する:短時間の診察でも要点を整理して伝える
- 生活習慣の工夫:水分管理や作業の区切りで症状をコントロール
- 情報収集:書籍やアプリで知識を整理し、症状を客観的に把握
これらを意識するだけでも、職場での緊張感や不安感を少しずつ軽減することができます。私自身も、リチウムを続けながら、これらの工夫で精密作業に取り組めるようになりました。完璧ではありませんが、無理なく働き続けることが可能になっています。
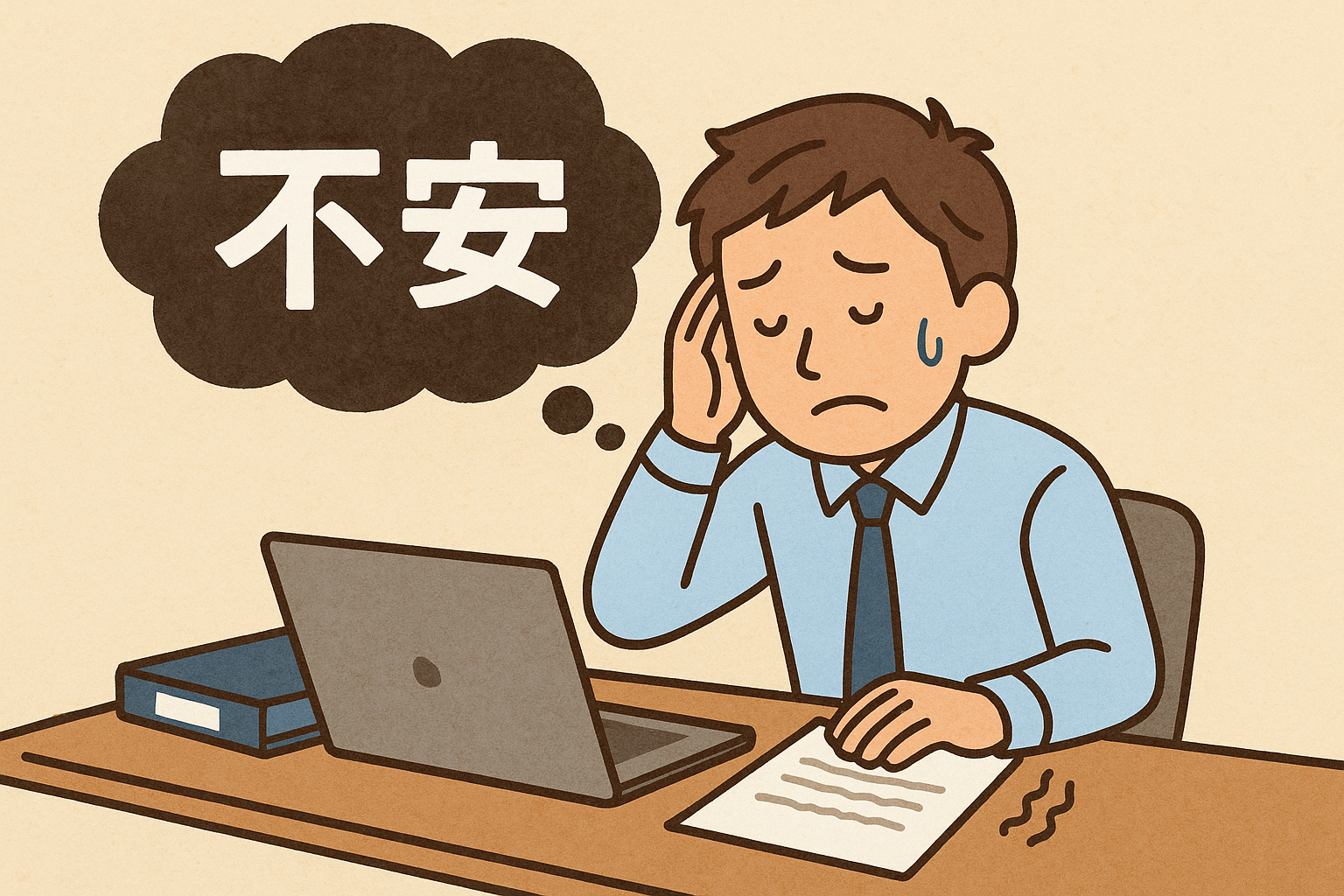
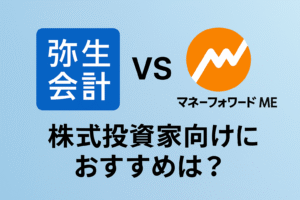




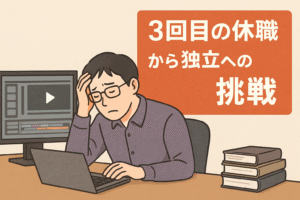
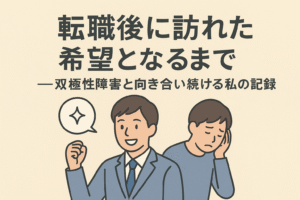
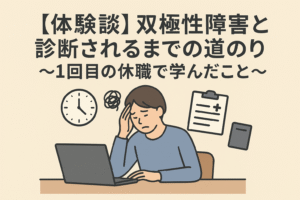
コメント